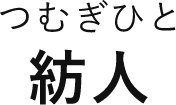教育資金贈与とは?最大1,500万円の非課税枠を活用する方法と注意点
最終更新日:2024年12月10日

執筆者
紡人(つむぎびと)発起人
中澤 寛(なかざわ かん)
中央大学を卒業後、金融のスペシャリストであるFP(ファイナンシャルプランナー)の事務所に業務提携パートナーとして参画。10年ほど在籍している中で感じた超高齢化社会の社会問題である「耕作放棄地」と「認知症によある」を解消するために、相続を包括的にサポートする『紡人(つむぎびと)』を発足。「最適解ではなく想いを最優先にしたプランニング」の考えのもと、相談者様に寄りそう相続対策・相続税対策をご提案いたします。
「子どもの教育費が増えて家計の負担が心配」「孫の将来に役立つ支援を考えたい」――そんなお悩みを解決する制度が教育資金贈与特例です。この制度では、祖父母が子や孫に対して教育費を贈与する際、最大1,500万円まで非課税となります。
しかし、適用には一定の条件があり、注意点を理解せずに利用すると贈与税が課税される可能性も。本記事では、教育資金贈与の仕組み、対象となる費用、活用のメリット・注意点、具体的な手続き方法を詳しく解説。未来への安心を手に入れるため、この記事を参考にぜひ正しく活用してください!
教育資金贈与とは?制度の概要を簡単解説
教育資金贈与特例とは、祖父母が子や孫に教育費を贈与する際、一定額まで贈与税が免除される制度です。最大非課税枠は1,500万円。受贈者は30歳未満で、教育目的で使用することが条件です。
この制度の目的は、教育費の負担軽減と相続税対策を同時に実現すること。資産を次世代に移転する際の重要な選択肢です。
教育資金贈与で非課税となる条件と対象費用
非課税対象となる費用は以下の通りです。
- 学校関連費用:授業料、入学金、施設利用料など
- 学習支援費用:塾や予備校の費用、家庭教師の費用
- 教材費や修学旅行費:教科書、制服、遠足代など
ただし、生活費や住居費、趣味の活動費は対象外です。また、贈与された金額が1,500万円を超える場合、超過分に贈与税が課されます。
教育資金贈与を利用する3つのメリット
- 贈与税がかからない:最大1,500万円まで非課税で贈与可能。子や孫の将来を直接支援できます。
- 相続税対策として有効:教育費として贈与した金額は相続財産の対象外となり、相続税の軽減につながります。
- 教育費の計画的な準備:将来の進学費用や留学費用を計画的に用意することで、家計への負担を軽減します。
教育資金贈与の落とし穴と注意点
- 専用口座を通じた管理が必要:資金は金融機関で開設する専用口座を経由して使用します。
- 使途の証明が必要:教育目的で使用したことを証明するため、領収書の保管が求められます。
- 期限を過ぎた場合の課税リスク:受贈者が30歳を迎えた時点で未使用の資金は課税対象となります。
- 適用条件の確認:制度適用には、金融機関や税務署への申請が必要。手続き漏れに注意。
教育資金贈与を始めるための具体的な手続き
教育資金贈与を利用する手順は次の通りです。
- 金融機関で教育資金専用口座を開設:贈与者が金融機関で専用口座を開設します。
- 贈与契約の締結:非課税枠の適用を申請し、必要な書類を提出します。
- 教育費の支払い:支払い時に専用口座を利用し、領収書を保管しておきます。
手続きが複雑な場合、税理士や金融機関に相談するのがおすすめです。
教育資金贈与を最大限に活用するポイント
- 早めの準備:教育資金が必要になる前に計画的に贈与を行いましょう。
- 使途を明確に:どの教育費に充当するか計画を立てることが重要です。
- 専門家に相談:税務リスクを最小限にするため、税理士やファイナンシャルプランナーに相談しましょう。
まとめ
教育資金贈与は、祖父母が子や孫の教育費を支援できるだけでなく、相続税対策としても有効な制度です。ただし、適用条件や手続きに不備があると、贈与税が課されるリスクもあります。
本記事を参考に、家族の未来を支える計画的な資産移転を始めてみてください。専門家への相談を通じて、制度を最大限に活用しましょう。
相続対策マニュアル配布中
相続対策、全62のノウハウを
全て共有いたします。
過去10年間の
ノウハウを惜しげも無く大公開
過去10年間で蓄積された相続の基本知識から応用編までノウハウを公開しております。『情報に価値はない』という考えのもと、ビジョンである『社会問題の解決』の一助として活用していただきたく、情報を大公開しております。ご希望の方は「資料請求」のフォームで進めてくださいませ。
資料請求フォーム